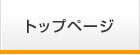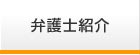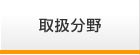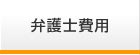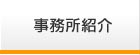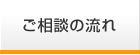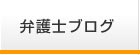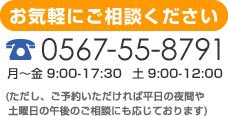3月 06 2015
弁護士費用特約でカバーされる範囲(弁護士費用特約の被保険者)
弁護士費用特約では,どの範囲の自動車事故までカバーできるのでしょうか?
保険会社によっても異なりますが,概ね次の範囲の方(被保険者)の事故についてはカバーされているようです。
① 記名被保険者(保険証券に書かれています)
② 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(子,両親,祖父母,きょうだいなど)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴のないことを意味する)の子
⑤ 上記①~④以外の方で,契約の自動車に乗車していた人
⑥ 上記①~④以外の方で,契約の自動車の所有者
以上①~④の方については,契約の自動車はもちろん,それ以外の自動車に乗車中の事故についても適用があり,歩行中や自転車に乗車中の事故についても適用があります。
どうでしょう?
なかなか広いなという印象ではないでしょうか?
「同居の親族」と「別居の未婚(これまでに婚姻歴のないことを意味する)の子」は含むということなので,たとえば,一度結婚したけれども離婚して実家に戻ってきた娘さんは含むけれども,離婚して実家とは別にアパート暮らしをしている娘さんは含まない,ということですね。
また,法人が記名被保険者となっている場合には,「家族」というものが観念できませんから,物損のほか,契約対象の自動車に乗車していた人のけが等について適用されるということになります。
ただし,自動車保険の約款は今後変わる可能性もありますし,会社によっても異なるでしょうから,まずは保険証券,パンフレットや約款をよく確認することが大切です。