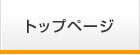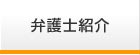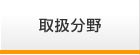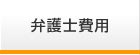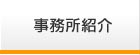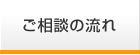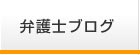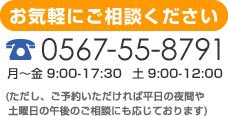7月 16 2015
自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を勧める理由
当事務所のホームページだけではなく,多くの弁護士・司法書事務所等のホームページにおいて,自筆証書遺言(全文を自筆で書き,印鑑を押す方法)ではなく公正証書遺言(公証役場で作成する方法)の作成が勧められています。
その理由としては,以下のものが考えられます。
①形式面でのミスがほとんど考えられない
自筆証書遺言でも弁護士・司法書士等の専門家に相談した上で作成されたものであればまだいいのですが,作成された方だけの判断で書かれたものには,「不動産の特定ができていない」「日付の特定ができていない」「相続財産に漏れがある」などミスが生じやすいです。
その点,公正証書遺言であれば,法律の専門家である公証人(裁判官出身者,検察官出身者,法務局出身者など)が作成しますので形式面のミスはまず生じません。
ただし,どんな財産があるのかはご本人しか分かりませんから,ご自分がどんな財産を持っているのかについては洗い出し作業が必要になります。
②原本が公証役場に保存されるため,遺言書がなくなったり,書き換えられたりするおそれがない
自筆証書遺言では,せっかく作成した遺言書が遺族に発見されない可能性や,発見者が書き換えたり,他の相続人に見せずに隠してしまう可能性があります。
この点,公正証書遺言では,作成時に原本と同様に遺言執行に用いることのできる正本・謄本をいただけるほか,原本そのものを公証役場で保管しています。
最近では,さらにデジタル保存の取り組みもなされていますので,「津波や地震で公証役場の入っているビルが倒壊した!」という場合でも安心です。
③自筆の場合に必要となる「検認」が不要
自筆証書遺言は,作成時には費用がかからず手軽ですが,相続発生後に「検認」手続きが必要です。
「検認」とは,遺言書を確認し,現状を確保する手続きで,家庭裁判所で行います。
検認手続きの申立てには,被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要になり,家庭裁判所から相続人全員に連絡が行くことになります。
申立てをしてから1か月~2か月後くらいの時期に検認を行う日が定められ,出席した相続人の面前で裁判官が検認をしてくれます。
このように,作成には費用や手間が少ない自筆証書遺言ですが,検認手続きに時間がかかってしまいますし,申立てを弁護士に依頼したり,司法書士に申立書類を作成してもらったりすれば費用もかかります。
特に時間がかかってしまう点は,無視できないデメリットではないでしょうか?
遺言書に封がされている場合(通常,封はされています。),検認を行うまで開封してはいけません。
したがって,封がされていると検認日までどんな内容の遺言書であるのか分からず,落ち着かない日々を過ごすことになります。
相続人に不安や手間をかけさせる自筆証書遺言よりも,公正証書遺言の方が優れていると言えるのではないでしょうか?
④無効の主張をされる可能性も小さい
自筆証書遺言では,「本当は別人が書いた遺言だ」「誰かに言われて訳も分からず書いたものだから無効だ」などと主張される可能性が,公正証書遺言に比べて大きくなります。
公正証書遺言では,公証人による本人確認を経ていますから「本当は別人が書いた遺言だ」と主張されることは通常考えられませんし,自筆証書遺言よりも無効の主張は難しいと言えます。